
サポートが理解しておくべき正しいローム、間違ったローム
いつもためになる解説動画でソロキュー戦士を支える Coach Rogue。
本記事では、彼が公開した「サポートはいつロームすべきか?」に関する動画をベースに、そのエッセンスを整理して紹介する。
サポートのローム原則:経験値最優先とロームタイマー
サポートの役割は多岐にわたる。視界管理、レーン主導、カバー、そしてローム。
ロームとは、自分のレーンを離れ、他レーンのガンクやカウンターに関与して数的有利を作り、試合全体の流れを有利にするためのアクションだ。だが、むやみに動けば経験値を落とし、味方ADCを危険にさらし、レーン主導権も中立オブジェクトも失うだけになる。
ロームには「すべきタイミング」が明確に存在する。その基準が後述するロームタイマー(ローム可能な時間帯)だ。ウェーブの押し付けとバウンスウェーブで生まれる隙にだけ動けば、経験値を失わずに影響力を広げられる。要するに、サポートは経験値を最優先し、経験値を落とさないロームタイマー運用こそが最も効率的なのだ。
なぜそう言えるのか。序盤の経験値がサポートの耐久力とスキル到達レベルを決め、8分のヴォイドグラブに直結するレベル6先行を生むからだ。以降、本文ではこの前提を支える根拠と、実戦での運用手順を紹介する。
なぜサポートには経験値が重要なのか?
サポートはミニオンで安定してゴールドを得にくいロールだ。よって、火力や耐久力をアイテムではなくレベルアップから引き出す必要がある。だからこそ「経験値を逃さないこと」が強さの源泉になる。
レベルアップで主に伸びるのはADよりも物理防御と体力。実例として、ノーチラスはレベル4→5の上昇だけで物理防御+4/体力+82を獲得する。サポートは装備で盛りにくい分、このレベルアップによる上昇がステータスの大部分を占める。
さらにメレー系サポートにはタンクするためのスキルがある。レオナのWは物理防御などを上げ、アリスターのRは被ダメージを割合軽減、ブラウムはEやWで同様に固くなる。ただしレベルが足りなければ、これら中核スキルのレベルアップが進まず、本来のタンク性能を発揮できない。序盤にXP効率の悪いロームをすると中盤で紙装甲化し、いわゆる0/10サポートに転げ落ちやすくなる。
要するに、サポートにとって経験値は極めて価値が高いのに、ここを軽視するミスが多い。これがCoach Rogueの出発点だ。
ヴォイドグラブでますます増加したレベル6の重要性
今シーズン、ヴォイドグラブの出現タイミングが6分→8分に変更された。これにより、デュオレーンで経験値をしっかり吸っていれば、8分に到着するウェーブでちょうどレベル6に到達できる設計になっている。
結果として、序盤に経験値効率を重視してロームしたサポートは、確実にウルトを所持してヴォイドグラブ戦に臨める。一方、経験値を無駄にしたサポートはレベル5止まりで最初の重要オブジェクト争いに入ることになり、ここで決定的な差が開く。
実戦でも、自分だけ先にレベル6に到達し、敵サポートが4〜5の間に中立オブジェクトを総取りする展開が起こり得る。動画は「レベル6 vs レベル4」の状況からドラゴンを含む中立を連続確保しており、レベル6先行が試合の流れを握る直接要因になっている。
要するに、8分ヴォイドグラブ=最初の分岐点であり、そこまでに経験値を落とさずロームすることが「ウルト所持での主導権」に直結する、というのがCoach Rogueの主張だ。
ロームタイマーの基本
ロームタイマーは「自分たちのウェーブを敵タワーに押し付けた瞬間に始まり、そのウェーブが自タワーに戻ってくるまで」続く。
ウェーブを押し付けると、あとからやってきた敵ミニオンが自軍ミニオンに引っかかって敵側寄りで停滞し、ゆっくりと自分側に返ってくるバウンスウェーブが始まる。これにより、自分は経験値を落とさずに動ける一方、敵サポートは同じタイミングで動くと大量の経験値を失うため、基本的には追従できない。
動画の例では、バウンスウェーブが返ってくるのに約50秒超かかっている。このウェーブの往復中は味方ADCはたとえ一人であっても後ろで待って処理すれば良い。
ロームタイマーを延長する小技
ロームタイマーを延長するコツがある。それは、プッシュの仕上げをADCに任せて自分は先にリコールを始めることだ。最後の数体をADCが処理してウェーブをタワーにクラッシュさせている間にリコール詠唱を進め、リコール完了の瞬間を「最後のミニオンが倒れる瞬間」に合わせる。こうすれば詠唱中にXPを取り切りつつ最短でベースに戻れる。
狙いは自分の時間を最優先にすることだ。序盤は「サポートの時間価値>ADCの時間価値」なので、ADCのリコールがやや遅れても、自分が先に復帰して動けるメリットのほうが大きい。先に戻れればタワー下でウェーブを受け止めてフリーズを作れるし、状況によってはそのままミッドにロームへ切り替える選択肢も取れる。
ロームタイマーは絶対ではない
LoLの唯一の原則「すべては状況次第」は、ロームタイマーにも当てはまる。
ロームタイマーは「守るべき原則」だが、「必ず従うべき絶対ルール」ではない。状況が極端なときは、意図的に破ってでも得られる見返りがある。Coach Rogue自身、「これはルールではなくガイドライン。例外は常に起こり得る」と前置きしている。
具体例が動画(9:50~)のラカンの試合。ボットでダブルキル後にフリーズを残し、次のウェーブの経験値が丸ごと1レベル分になる場面だったため、本来は即リコール→ボットでウェーブを受けるのが定石。しかし同時に、ミッドの敵カタリナが低HPかつTPなし。ここでCoach Rogueはあえて「ルール破り」を選択し、大量の経験値を捨ててでもミッドへ。たとえキルにならなくてもリコール妨害でウェーブ損失を強要でき、ミッドのレーン状況をまるごと変えられる状況だったからだ。
結果として自分は1レベル分の経験値を失うが、敵ミッドに同等以上の損失を与えることを優先。しかもボットのウェーブは味方ADC(ヴァルス)が全回収したため、チーム全体ではミニオン損失なし。サポート本人のレベル6到達は遅れても、敵ミッドが失うゴールドと経験値の方が致命的という判断だ。だから「敵ミッドをへこませる確度が高い」なら例外的にロームタイマーを破る価値がある。
要するに、
原則:序盤は経験値を最優先し、ロームタイマー内で動く
例外:敵ミッドが低HP・TPなしなど、高確度でレーン崩壊を起こせるときは自分の経験値を捨ててでも介入(ただしチームとしてのミニオン損失は別ロールなどが埋め合わせるのが前提)
ということだ。
レベル6以降のローム
ここからは基本的に常時ロームしていい段階に入る。理由は経験値の性質にある。
ミニオンから得られる経験値は常にフラットだが、チャンピオンキルの経験値は対象のレベルに応じてスケールする。
序盤はミニオン由来の経験値比重が大きいが、時間が進むほどファイト参加=戦闘関与で得る経験値が主体になる。だから後半は、ロームタイマーに神経質にならずとにかく戦闘に関与していけば自然と経験値が入る。
実戦でも、序盤に経験値を優先して先にレベル6へ到達できると、中立オブジェクトの主導権を一気に握れる。この動画でCoach Rogueは「自分レベル6、相手サポレベル4」の状況からドラゴンやグラブなどを総取りできている。以降はロームでの主導とファイト参加がそのまま経験値と勝ち筋につながっている。
Coach Rogueについて
この動画の作成者であるCoach Rogueは、元プロプレイヤーとして7年間にわたりリーグ・オブ・レジェンドの競技シーンで活躍し、現在はフルタイムのコーチ兼コンテンツクリエイターとして活動している。
すべてのランク帯(アイアン〜チャレンジャー)に対応した個人コーチングを行っており、その実績と指導内容は、約1,000時間以上におよぶPatreon上の録画アーカイブにまとめられている。これらのセッションはロール別・ランク別に整理されており、プロチームへのコーチングセッションも含まれている。
YouTubeでは、実戦で役立つマクロの知識やメカニクス、コンボをわかりやすく紹介しており、今回の記事もその動画からの内容をもとに構成されている。詳細なコーチング情報などは、Coach Rogue氏のYouTubeチャンネル
および動画概要欄のリンクから確認できる。
現代のサポートは「最強のロール」と言われるほど試合への影響力が大きい。読者諸賢が知る有用なローミングテクニックも、ぜひ教えて欲しい。
ロームで試合に差をつけロームでござる。
おすすめ関連記事




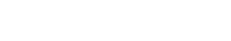





コメント